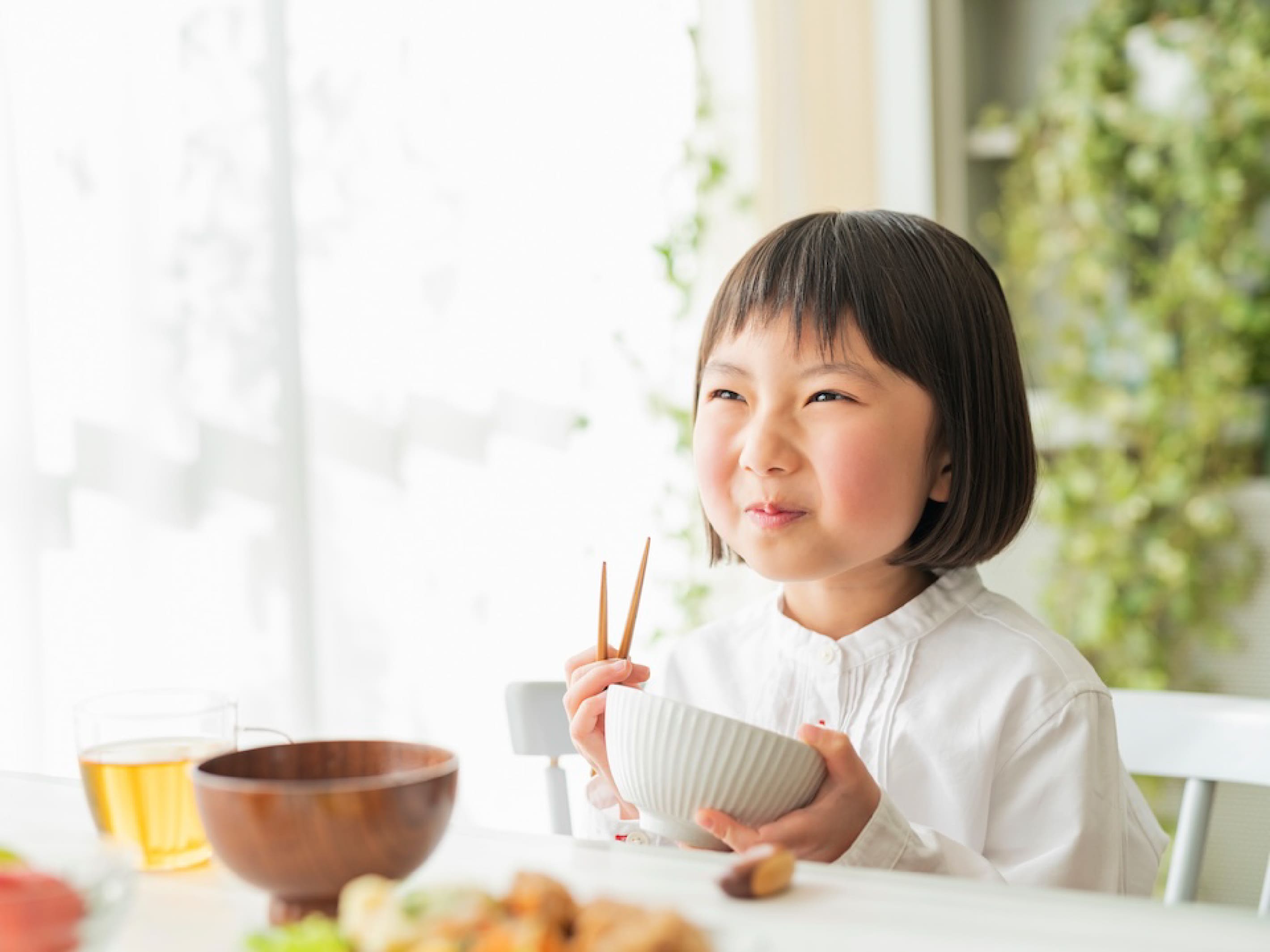◉ 西洋料理にも中国料理にも
出汁はあり、うま味がある。
「もちろん、日本の出汁には、うま味があります」と断わったうえで、野﨑さんは続けます。
「けれど、うま味に関していえば、西洋出汁であるフレンチのブイヨンや、中華出汁である中国料理の湯(タン)ほうが強いですよね」と。
出汁とは、何か? 連載第2回目に定義した、天然素材の持つ<うま味>成分を溶出させた汁で、料理全体の味を引き立てるもの、と言えます。
ではうま味とは、何か?
食品に含まれるグルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸にナトリウムやカリウムなどのイオンが結合した塩類(グルタミン酸ナトリウムなど)によって生じる味覚であり、料理の深みやコクを引き出す重要な要素と定義できます。
野﨑さんは、簡潔に補足します。「アミノ酸ですよ。酸っぱさを感じない酸、それがうま味です」
グルタミン酸が含まれる食材としては昆布がよく知られていますが、玉葱や人参、セロリといった西洋野菜にも、長ネギや白菜といった中国料理でよく使用される野菜にも含まれています。
同じようにイノシン酸は鰹やイワシなどの魚類だけでなく鶏肉や豚肉、牛肉にも。またグアニル酸は干し椎茸に含まれますが、西洋料理で使われるドライトマトにも含まれています。
そして、グルタミン酸の昆布とイノシン酸の鰹節を合わせて一番出汁を取るように、これらは組み合わせることで、うま味が飛躍的に増すという相乗効果もあります。
さらに西洋のブイヨンや中華の湯には、日本の出汁よりも各種アミノ酸が数多く含まれており、より複雑な味、いわば強さを持っています。
出汁やうま味は、日本料理の専売特許ではありません。それらは西洋料理にも中国料理にもあり、しかも和食にはない強さを秘めています。
だから差別化ポイントにはならない、と野﨑さんは捉えているのでしょう。では、何をアピールすべきでしょうか?
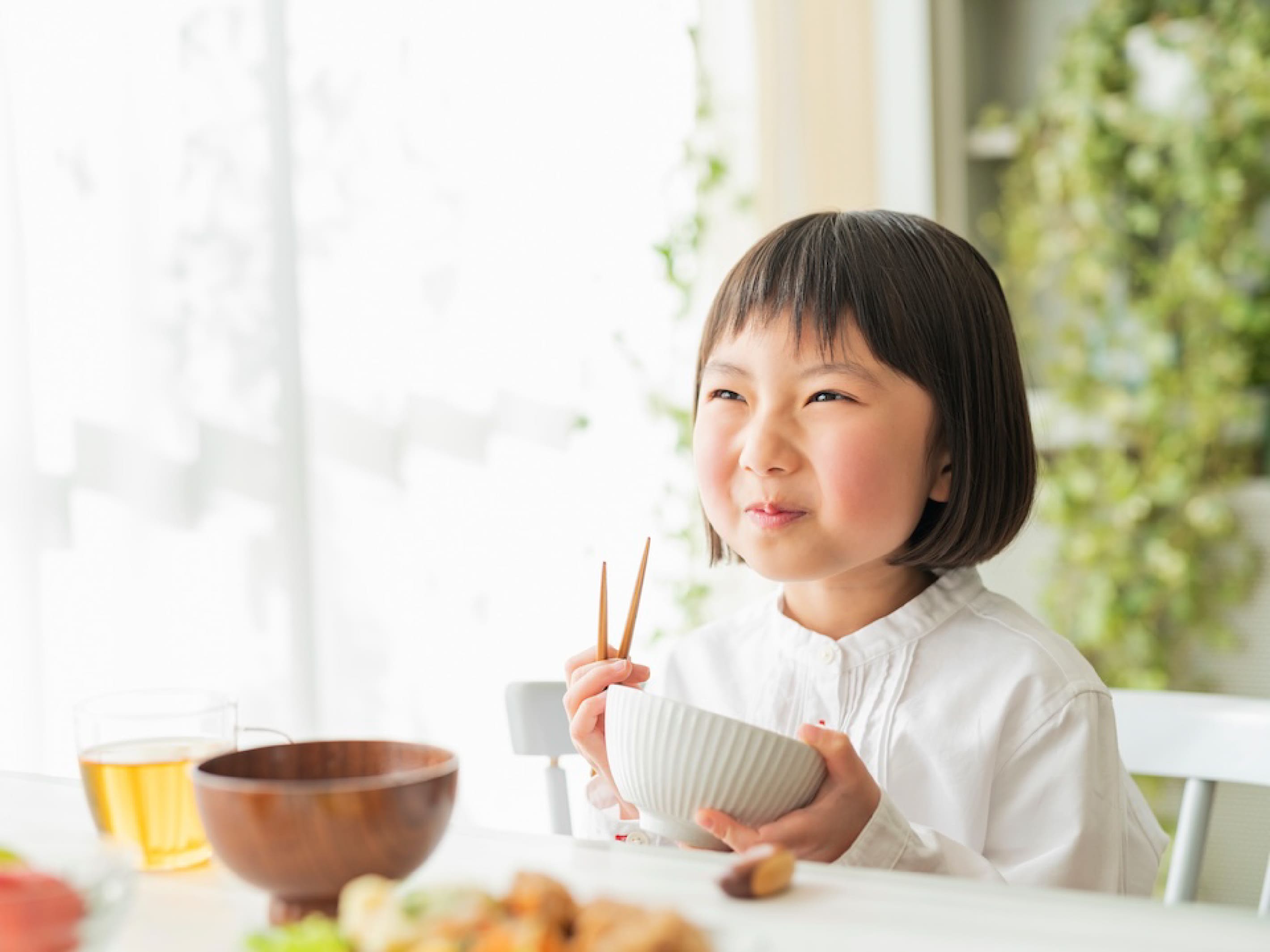
◉ うま味のその先へ。
五味五色という料理用語があります。
そもそもは陰陽五行説に由来する言葉ですが、この五味の部分を、日本では冒頭に触れた基本味覚——甘味・塩味・酸味・苦味・うま味の五つの味覚を指すことが多いようです。
一方、上記の曹洞宗のサイトでは、おそらく成立した時代が違うからだと思われますが、うま味が入っておらず辛味が入っています。
また、渋味や、最近では脂肪味を付け加える方もいます。辛味や渋味は味覚というよりも痛覚ではないかという人もいます。
そして野﨑さんは基本五味に淡味、辛味、渋味を加え、さらに大切な、忘れてはならない味があると言います。
それは「人間味」だと。
「たとえば、夫や子供の体調がすぐれない日、お母さんは『まずは消化しやすいものを』とか『何か元気のつくものを』と考え、腕をふるいますよね。
人間味は、目的に応じた味と言いますか、食べる人のことを思う気持ちが、料理する人の味となってあらわれます」
日本政府観光局の発表によると、2025年4月の訪日外客数の推計値は390万人を突破しました。単月として過去最高を更新しそうです。
訪日外国人観光客が日本の良さとしてまず挙げるのが、街の清潔さや正確な公共交通機関、礼儀正しい国民性です。そして文化や自然、食べ物も日本独自だと高く評価しています。
農林水産省では、「日本料理に大切な五法・五味・五色・五感」と題し、次のように記事を結んでいます。
出典:農林水産省ウェブサイト(https://www.maff.go.jp/j//yusyutu_kokusai/washoku-world-challenge/learning_04)
——料理を作る者は、色々な事を考えそして、料理を創りあげることが大切です。料理を創るとは、いかに食べ手側の思いを読んで作り上げるということであり、日本の「おもてなし」と言えるのです。
*
淡味、そして人間味の時代へ。次回は本連載の最終回となります。「出汁の実践。おいしい出汁の取り方」をレクチャーします。